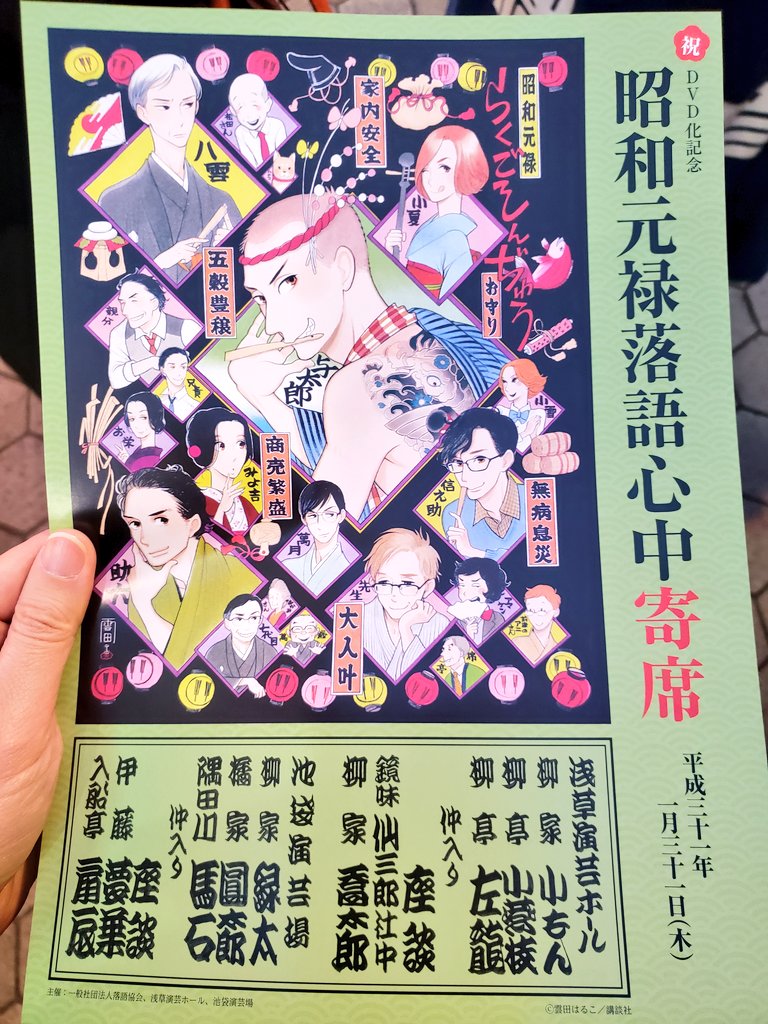投稿日 2019-08-09 / 最終更新日 2021-01-03

新海誠作品で描かれる、東京の、新宿の風景がたまらなく好きである。
そのとき持てる最高の技術を結集して造られた高層ビルや巨大建造物やマンション。
その窓に輝く光の一つ一つに、働いている人や生活している人の家庭があり人生がある。
世界一乗降客数が多い新宿駅の人々の通勤風景や街の雑踏。
捨てられたゴミで汚れた街角やアスファルトの破れ目から元気に顔を出す雑草。降り出した雨が道路を叩きあっという間に煙となって、アスファルトから匂いを引き出し、太陽と熱と雨の混ざった香りを立ちのぼらせる。
空は毎回違う青に染まり、雲は毎回違う形で空を泳いでいく。
都市に差し込み都市を照らす光は、まるで神からの祝福のような神々しさに満ちている。
“嫌悪の対象”となることが多い「東京」の風景を、新海監督はなんて美しくなんて猥雑で、なんて日常に描くのだろう。
新海誠最新作『天気の子』は、まさに「今」と「今年の夏」にピッタリの物語であった。
!以降は『天気の子』、他新海作品のネタバレを含みます。映画未見の方はご注意ください!
2019年8月12日04時、帆高の島でのバックグラウンドと圭介について追記しました。
Contents
それは、どこまでも果てしなく「東京」だった
私は東京が、新宿が好きである。
上京して20年。通勤や居住など殆どの年数をほぼ新宿とともに生きてきた。
マツコさん曰く新宿は「どんな人種(エリートも学生も夢追い人もオカマもホームレスもヤクザも)でも受け入れてくれる街」だという。
都庁という政治的機能も、大手企業も、怪しい会社やお店も。ヤクザの抗争的な事件も時折ある。
決して美しく都会的なだけの街ではない。
けれどここではどんな生き方も許容される。
それがモラル的に正しいか正しくないかは別として、とにかくどんな人にでも居場所がある。どんなバックグラウンドを持つ人間でも受け入れられる街なのだ。
他の新海作品『秒速5センチメートル』『言の葉の庭』『君の名は。』でも新宿は美しく描かれているが(同じ場所でも特に『秒速』では大人タカキの暗鬱とした心情の象徴として登場したりしているが)、『天気の子』では惜しみなく新宿の”街”の美しさと汚れ具合を描いていて驚いてしまった。
それは、あまりにも「普段見慣れている風景」だったのだ。
歌舞伎町が舞台の作品といえばつい先日新作公開された『シティーハンター』が頭に浮かぶ。
40代前後の青春であり新宿が舞台である『シティーハンター』でも描かれなかった、「バーニラバニラ♪」の宣伝カーやらラブホテル街(TVアニメではラブホテル街はよく出てくる)。
“歌舞伎町の猥雑さ”を――もちろん企業コラボということもあるが――あそこまで出し生々しく描いていることが本当に凄い。
あれは誇張も美化もされていない、新宿を歩いていたらいつも目にする景色そのものだ。
ちなみに代々木は専門学校に1年間毎日通っていたし、フリーランスになってから8年ほど代ゼミの裏に事務所を借りていたので、お昼や飲みでも利用していた“聖地”の廃ビルはあまりにも馴染み深い。
新海作品では”東京の象徴”のように描かれるドコモタワーは、新宿駅への往復の際いつも見上げていた。
田端駅のマンションには2年ほど住んでいて陽菜の家の辺りは山手線通勤電車の中からよく見ていた。ラストシーンでは私が住んでいたマンションはすっかり水没してしまっていたけれど(苦笑)。
そんな訳で今作は過去作以上に自分にとってあまりにも「私がよく過ごした(過ごしている)知っている場所」すぎて、一層世界へと入り込んでしまったのである。

少年少女が大人になっていくその過程に「親」の存在が必要ない力強さ。
主人公である帆高も陽菜も「親」については作中で殆ど描かれないし語られない。
2人はどんな家庭に育って、親はどんな職業で、どんな幼少期を送ったか。
陽菜の母はいつからどんな病気で亡くなったのか。
親のかわりに出てきてもよい筈の「親戚のおじさんおばさん」といった存在も、まったく出てくる気配すらない。
帆高は家出をするほど島や家が嫌で帰りたくないし、陽菜は”事情”があって弟と住んでいる。それぞれ互いがほんの少しだけ互いの事情を聞いて「そうなんだ」で通じ済んでしまう。
それは決して相手に無関心なのではなく
「よくあるよね」
「私もそんな感じ」
と受け入れているからだと思う。
「これ以上は入り込まないほうがよい」という人との適切な距離というものを、哀しいほどに感覚として理解している。
陽菜の家には「父親」の存在がまったくない。
仏壇らしきものもなく、父親である人間にも連絡がいかないということは、恐らく離婚だと推測される。姉弟にとって「頼る大人」として登場しないのだから、母が生きているずっと前から父親はいない。長年母子家庭だったのではないだろうか。
帆高も別に「お父さんは?」とは聞かない。
これが、今の子どもたちにとってごくごく当たり前にある日常なんだと思う。
ごくごく『普通』に両親が揃っている家庭というのはあまりない。
私の周囲も、親が何人もいる人も、兄弟の母親が皆違うという人も少なくない。
だからお互い家庭環境に深く触れることもなければ、「それは違うよ」「普通はこうだよ、こうすべきだよ」なんて相手に説教をすることもない。
親について子どもたちの力ではどうにもならないことを、子どもたちは知っているから。
元々「家族」が蚊帳の外にいがちな新海作品だが、今回はもっと「家族」は外側にいた。
アイデンティティの確立
人間とはいつ“自分は自分”と受け入れ、自己を認識しアイデンティティを確立するのであろうか。
私は、きっとそれは「血縁とは無縁の第三者が“自分を承認してくれた”とき」だと考えている。
私自身機能不全家族出身者である。存在を肯定してもらったことがなく、己の境遇に耐えきれなくなった私は14歳の時一旦命を放棄した。
私の人生は割愛するが、血縁者による肯定や承認がされない人間にとって自身の存在定義やアイデンティティを「親や先祖の存在のおかげ」「血の繋がりに感謝しろ」と言われると本当に居心地が悪く辛いものがある。
例え血縁関係者に自己の存在を否定され承認されなくとも、愛されなくとも、誰もがこの世に生まれ生きていてよい人間だ。
家族の絆、温かさ。
それは憧れでもありとても“正しい”ことでもあるけれど、そういう家庭ばかりではない現代において「親」の存在を圧倒的に無視しして子どもたちが大きく成長していく様が描かれる物語は、なんと痛快だろうか。
血縁ではない他者との繋がり。
家族ではないけれど、家族のような存在。
家族以外の人間関係に助けられ生きること。
それは今の時代を生きる人間同士の関係であり在り方でもあるのだと思う。
10代を取り巻いている「今」
今の子たちは本当に”間違う”ことを恐れている。というのはこの数年専門学校で非常勤講師をし、10代の子たちに触れて感じることだ。
正解であることが大切で、「なぜ?」「どうして?」の過程は考えない。
デザイン制作物Zにたどり着く道と制作物Yにたどり着く道はAでもBでもCでもDでもよいのに「Zにたどり着くにはA以外は不正解ですよね?」となってしまう。正しいツールで正しい順番でなくてはダメなのだという強制力を感じるようになってしまっているようだ。
一方人間関係はSNSで繋がっていて、学校以外の時間でも人と人とが密接だ。
友人や教師、親から“ずっと見張られている”感覚があるからかもしれない。
SNSが発達する前は見えなかったものも望む望まないにかかわらず目に飛び込んできてしまう。
世界にしょっちゅう起こる悲劇や炎上、大人たちが本当は全然大人じゃないこと。
イジメはいつの時代も陰湿でどうしようもないものであるが、SNSによってさらに簡単に仲間外れやイジメが起こる。
大人ならお金を使って趣味や場所などにうまく逃げられることもできる。必ず「みんな」と仲良くする必要もない。
けれど学校は集団に属して同調することを求められるし、子どもたちにとって世界は学校と家庭が殆どであるから、「”同調圧力”から遮断され安らげる、完全に一人になれる時間や空間」というものは、多分どこにも存在してない。
「東京に来てから息苦しくなくなった」
帆高のセリフがある。
地方出身で高校生まで田舎を転々と過ごした私はその言葉に大いに頷いた。
小さな集落になっていくほど、人間関係は恐ろしく密だ。
各家庭の家族構成や状況を町の皆が知っている。誰がどこで何をしていたか、翌日には町中の噂になる。
地主や町会議員など、親の職業の偉さが子どもの偉さに直結して序列ができている。
その地域の人間はほぼ同じ小中高(高校がないところも当たり前にある)に通うし親や祖父母も同じ学校の出身者。
人の動きは殆どなく転校生は滅多におらず、よそ者はいつまでたってもよそ者だ。
人間関係には殆ど変化がない。
自分の生活を知られている。親のことも子のことも成績や交友関係まで街中が当たり前に知っている。
「ただの一人になって自由になれる時間」がないということ、「誰の目も気にしなくていい時がない」というのは大変な息苦しさだ。
帆高の卒業式を見れば、帆高の住んでいた「島」がどれだけ小さなコミュニティなのかが伺える。
10代にとってのSNSと、田舎のそれらは少し似ているかもしれない、と思った。
どこからもはみ出さないために、誰にも”悪口”を言われないように、イジメのターゲットにならないように、自分の行動や言動に細心の注意を払い息をひそめて生きていく。
本当に自分が感じたことや思ったことに蓋をして。
自分の内側を、”外”の世界へ出す
帆高も陽菜も10代の子どもだ。
しかし親や地域からの抑圧、子どもとして親に甘えることが出来ないままに勝手に思春期へと突入してしまった。
陽菜は母の死後きっと一度も泣いていない。
彼女は精一杯お姉さんであり続け、年齢を偽って生活のため頑張る。
母親の死後も家を借りていられること、弟が部活以外のスポーツをできる程度にはとりあえずのお金はある(母の蓄えや保険もあるだろう)。
陽菜は母の死後バイト漬けだったという凪のセリフ。
子どもだけでこれからも生活してくことや弟の進学を考えたとき、陽菜はどんな仕事か理解した上で、よりたくさんのお金のために風俗の世界へ飛び込もうとする。
陽菜は帆高と出会ったとき、もうすぐ18歳と口にした。
それにしては幼い顔立ちで描かれていて、終盤で彼女の本当の年齢は15歳なのだとわかる。まだ、中学校に通っている筈の年齢だ。
心がずっと島の外へとあっただろう帆高と、母が入院した頃には既に学校に行かず働き始めたであろう陽菜には、他愛ない話をして笑い合える友人も、何かを相談できる大人もいなかったんだろう。
あの島には、そもそも帆高と同じ年の子はいないのだろう。
オープニングでも島の回想でも、穂高の顔は傷だらけだ。陽菜を助けるとき馬乗りになられた時の彼は、殴られなれているようにも見えた。
私は最初帆高は親から虐待をされていたのかなと思った。でも虐待された人間は、まず親へ逆らう精神力を徹底的に奪われる。親がいないと物理的に生きていけないから。
だから、もしかしたら彼は適切に反抗期を迎え、閉塞感や孤独を分かち合える人がいないが故に思春期になったら喧嘩っぱやくなり、それゆえに「大人の言うことを聞かない悪い子ども」として教師に殴られたり悪く言われていたのかもしれない。
親も「お前が悪い」というばかりで、ただ咎められ怒られただけなのかもしれない。お前は我が家の恥だとか、そういう物言いをしていたのかもしれない。
チンピラや警察官に対して臆すことなく悪いとも思わず向かっていくのは、島で「大人」たちが彼を”正しさ”で服従させようとしてきたからではないだろうか。そして「大人」は誰も理解したり助けてくれなかったのだと思う。
3日間、スープのみの夕食を摂っていた少年にハンバーガーを届けた陽菜。
帆高にとって東京で受けた、もしかしから人生で初めての他人から受けた優しさであり「今までのどの食事より美味しかった」ハンバーガー。
彼の”どこにも置き場所のなかった心の孤独”が伺える。
風俗で働くため、怪しげな男たちに雑居ビルへ誘導されている陽菜。
彼女がハンバーガーをくれた女の子だとわかり、帆高は拾った銃を使い彼女を救い出す。しかしここで陽菜はムリヤリ連れていかれた訳ではないことがわかり「危ないところをありがとう」とならないのが、この作品は”王道”はいかないんだぞ、と予感させてくれる。
そこから2人の道は絡み合い、狭い世界を飛び出した帆高の東京での人生が始まっていく。
閉じた心の世界にいた帆高と陽菜、それぞれの”世界”に変化が訪れする。
心にガードをせずにいられる人たちとの出会い。
他者との関係を育みながら『自己』を確認し、自分の足で力強く世界の外へ向かい、立とうとしていく。
勝手に”大人”になってしまう大人たち
子ども時代にきちんと”子ども”でいることが出来なかった人間は、どうやって大人になればよいのだろう。
甘えたり頼ったりする大人がいないまま、お手本がいないまま、体は成長して勝手に大人になっていく。
いつの間にか、大事なものも、背負うものも、責任も、勝手に増えていく。
しがらみも、手放せないものも増えていく。
『天気の子』作中に描かれるいわゆる“ダメな大人”の代表に圭介という存在がある。
未成年にご飯をたかったり家出少年だとわかっているのに特に事情は聴かず雇って薄給で働かせたりと「大人」としてダメな点をあげだしたら色々と出てくるのだけど、彼は東京に家出してきた帆高に対し深く干渉することなく仕事を与え(超薄給だけど)家と食事を共にする疑似家族となる。
「大人」としてみたらダメだけど、”正しい”ことを強要せず、深く事情をきくことなく置いてくれる。ありのまま受け入れてくれる大人の存在は、本当にホッとする。
圭介が、かつてそういう大人に助けられたのかもしれない。
帆高や陽菜の「親」がほぼ描かれなかったのとは対照的に、この物語では圭介の「家族」が描かれる。
彼の妻は既に故人。喘息持ちの娘は義母に連れていかれなかなか会うことができない。
だけど娘の前では彼は精一杯「よい父親」であろうとするし、妻に対してもずっと一途だ。娘も父が大好きである。
娘のための三輪車や遊び道具が事務所の入り口にあって、娘と再び一緒に暮らせる日を待っている。
自分が一番大切にしたいものを、優先すべきものを圭介は持っている。
だけど彼は一向に煙草を手放せない。義母にそのことを突っ込まれるも弱気な返答で、喘息の娘のために吸わないと決意していても事務所の引き出しの一番上にはいつも煙草が入っている。
圭介の血縁である夏美。明るくてあっけらかんとしてる彼女だけれど、メイン収入源である仕事はおそらくあまり良いものではなくて、就職活動をしているけれどうまくいかずに疲弊している。
その疲弊を帆高や陽菜には決して見せない分、圭介よりはずっと大人でもある。
だが彼女はまだ圭介のような”何を差し置いて絶対に守りたい・守らなくてはならないもの”は持っていないのだ。欲しいものに「ちゃんとした彼氏」とあげるてので、少なくとも今の彼氏は「ちゃんとした彼氏」じゃないんだろう。
物語の後半、圭介は娘と暮らせるかもという目の前の希望のため、厄介者である帆高を切り捨てる。そしてこの異常気象は陽菜の影響であり、陽菜一人の犠牲で済むならそれでよいと考える。
仕方ないと思っている一方で、酒をあおる。
頭では仕方ない、と思っていても、心では違う・それは間違っていると感じていることからきている行動だろう。
夏美はそんな圭介を叱りつけ帆高の逃走を手助けする。
ヤバイなーと言いながら、帆高と一緒に悪事を働いてくれる大人だった。
夏美にとって、帆高と陽菜は何をしても「守りたい」と思える存在になっていたのだろうから。
廃ビルで帆高を見つけ圭介がかけた言葉には「大人ならそういうしかない」とか「ちゃんと言い切れないもどかしさ」とか「でもやっぱり彼の想いを大切にしたい気持ち」を感じる。わかっていても単純な感情だけでは動けない。一貫できない言葉や姿勢や迷い、体面とか矛盾とか苦しさが滲む。
そんな圭介の在り方や言動を、カッコ悪いとも間違っているとも思わなかった。「そう言うしかないだろうな」と思った。
「そんなに大事に思える相手がいるのがうらやましい」と安井刑事に言われたとき圭介が流す涙。妻や娘への気持ちが溢れ出す。
一緒に怒られてやる、という彼の気持ちには嘘がはなく、圭介にとって「大人としてできる」精一杯の言葉だと思う。
でも、帆高の、陽菜に会いたい、ただそれだけを願う真っすぐすぎる気持ちには届かなかった。
「陽菜に会いたい」と痛切に真っすぐに気持ちを叫ぶ帆高を前にして、大人の理屈で「仕方ない」とか「終わったことだ」「どうしようもない」と見ようとしなかった圭介自身の気持ちが揺さぶられる。
妻への想いを、そんな風にストレートに、圭介もきっと言いたかった。
オカルト記事の仕事をエンタメを提供していると言い、天気の巫女の話をあほらしと言う彼だから、陽菜が空にいることは信じていないけれど、それでも帆高はいなくなった陽菜に「もう一度会える」と信じている。
自分がもし妻と会えるなら、その方法があるのなら、彼は何としても会おうと思うだろう。
帆高が見せる陽菜への真っすぐな想いは、圭介が妻や娘に対し「こうでありたい」と願う自分の姿そのものでもあるのだろう。

「”それでも構わない”を自ら選び取ること」への力強いエール
帆高の行動は終始とても子どもじみていて、いつもどこか”間違えて”いる。
だけどとてもとても必死で、その時々の彼の行動はいつも彼自身の心に誠実で嘘がない。何よりも”行動力”がズバ抜けている。
あの狭い世界から抜け出したい。光を追いかけていきたい。
目の前で危険な目に遭いそうな子を放っておきたくない。
彼女の力は誰かの役に立つ、自分はそれを手伝いたい。
陽菜と凪を守るため、警察官を相手に立ち向かう。
陽菜を取り戻したい一心で、線路を走り拳銃を放ち空へと向かう。
いわゆる”反抗的=不良”タイプには描かれていないのに、彼はこれだけの行動を起こす。
これは2回目の鑑賞後「自分の内側を、”外”の世界へ出す」へ追記したが、彼はきっと島で「大人達にとって」とても反抗的な子どもで、「大人」たちに”正しさ”で殴られてきたのだと思う。
彼の根本は「大人」を信用していない。それが公権力であったとしても。
家出して東京で”お金がたくさんいる”ことはわかっていても、まったく計画的ではない。圭介からの”手切れ金”を宿と食事に殆ど使ってしまったことも、この状況を打破するために銃を使うことも厭わない。
そういう素直さと無知さ(というよりお金の使い方を知らない)は、島育ちだからこそ養えたものでもあるだろう。
彼は”今”の自分の気持ちに素直で、とても無鉄砲だ。
自分がどう思われるか、その後どうなるかなんてことは気にしていない。
「こうしたいんだ!」「こうするんだ!」それだけだ。
例え世界のカタチが変わってしまうとしても、帆高は陽菜が存在するいる世界を選びとる。陽菜のいない世界は嫌だと思ったから。
“自分の意志”を確かにとらえ、少年は階段を駆けあがる
『秒速5センチメートル』『星を追う子ども』など新海作品で描かれる誰かの感情と地面はとても近い。
空は遥か高く遠く、人間の手が及ばない領域として描かれる。
『雲のむこう、約束の場所』でも空は乗り物がなければ行かれない場所である。
階段(あるいはそれに相当する場所)は”降りるもの=別れ、決別”として描かれている印象を受ける。
『言の葉の庭』では階段を駆け下りるタカオとユキノがようやく本当の気持ちをぶつけあう。2人が結ばれることはないという予感をさせつつ。
より多くの人に届けるように作られたであろう、そして実際に多くの人の心に届いたであろう『君の名は。』では、それは変化した。
誰もが印象に残っているのは、何よりもラストだろう。
“ずっと探していた”互いを見つけた2人。
瀧は階段を下り、三葉は階段を上る。
この先で2人が結ばれるであろうと確信できる、未来的な終わりだ。
『天気の子』は空へ、人の手が及ばない現象へと飛んでいく。
帆高は銃を使うことが悪いことであると明確に認識しながら、銃によって大人を足止めし、陽菜を取り戻すために廃ビルの壊れた階段を強い意志で駆け上がっていく。
しっかりと顔を上げ、子どもの自分を捉えていた世界から一度足を離して。
そうして空でつかまえた陽菜とともに今度は空を足元にして、2人で”世界”へと帰ってくる。お互いに気持ちをはっきりと言葉にして。
島と両親への感覚の変化、卒業後「家出ではない形」での上京。
世界に戻った彼は他者に承認された等身大の自分をきちんと認識して、少しだけ大人になっていた。
主人公であった15歳と16歳の少女と少年は、ラストシーンでようやく制服を着る。
大人になるということは、世界に折り合いをつけて勝手に諦めたり冷笑したり仕方ないと”大人ぶる”ことではない。
自分を取り巻く世界で足掻きながら譲れないものを守りながら、時には後退したり頑固に世界と喧嘩しながら、目の前の現実を一つ一つ生きていくことだと思う。
壊れた階段ではなく足元が確かな階段を踏みしめながら、一歩ずつ人生の階段を登っていく。
だからこのラストは、彼らが大人に怒られて見守られ助けられながらきちんと”学生生活”を送った証なのだ。
それが楽しかったかよい時間であったか、彼彼女にとって幸福な時間だったかはまた別の話だけど、その年齢でしか経験できない”子どもが子どもであるべき時間”をちゃんと過ごして、そうしてもう一度世界に向かっていくのだ。
島に戻った帆高はやっぱり息苦しいことや辛いことがたくさんあったと思う。そしてやっぱり島では孤独だったと思うけれど、彼には陽菜や凪や圭介や夏美と過ごした確かな時間がある。陽菜が世界に存在しているという事実がある。
高校卒業後は東京に行く、と目標があった彼にとって、もう島に来る前ほどの閉塞感も島のしがらみに縛られることもなかっただろう。
ただ「初・告白?」とドキドキして浮かれている帆高に、彼がちゃんと子どもらしい子どもさを持ち続けていることにホッとした。
”世界”は一瞬で変わる
”世界”はとても広くて、とても狭い。
世界がずっと雨になってしまったとしても、本当は彗星落下の際自分がこの世の人間じゃなくなっていても、それはもう誰にも「ほんとう」はわからない。
自分の外側で起こる世界の変化は一瞬で劇的に変わるものではなく、長い長い歴史や小さな偶然や出来事の積み重ねの結果だ。
でも、自分自身の世界は一瞬で変わる。
たった一人の誰か。たった一度の強烈な体験。
そんな大きな経験をしたとき、人はそれまで過ごしていた世界がひっくり返るだろう。
誰かやなにかが、自分が生きる”世界”を大きく変える。
自分と世界の関わり方が変化して、見える景色が変わっていく。
外から、他者からはわからなくても、確実に、鮮やかに、自分の世界は変わってゆく。
人生に正解なんてない。万人に好かれる生き方なんてものもない。
ただ、自分や大切だと思う人。大切だと思うこと。大切にしたいこと。
それはきっと誰の人生にも訪れることだ。
もしもまだそんな体験がない人は、きっとこれから出会うだろう。
世界は、そういう「大切な人・もの」を持っている人であふれている。
大切な人やものごとがある。それを大切だと思う自分自身がいる。
大切な人やものごとのために、何ができるだろうか。
それは恐れずに、自分の気持ちに素直になってみること。
一歩踏み出してみること。
そして、知らない誰かにも嫌いな誰かにも、そうやって大切にしていることがあるのだということを理解すること。
世界はそういう人やものでいっぱいだ。
大切なもの大切だと、胸をはっていいんだ。
大好きだと、大事だと、叫んでいいんだ。
そんな力強さを、若い人たちへのエールを、私はこの作品から受け取った。
変わりゆく「東京」のかたち
東京の姿は日々目まぐるしく変化している。
『天気の子』の聖地である代々木の廃ビルは既に解体工事が始まっている。
「天気の子」聖地・代々木会館の解体始まる 「傷だらけの天使」にも登場
都庁、コクーンタワー、バスタ新宿。六本木ヒルズやスカイツリー。都営大江戸線に副都心線。築地市場から豊洲市場。渋谷駅。
2020年東京オリンピックに向けて駅の案内板がかけ替えられていたりと、小さく、でも確実に昨日と今日で変化している。
『君の名は。』では糸守の喪失を“知って”いる瀧が「東京もいつか失われるかもしれない」と就職活動で語るシーンがある。
東日本大震災を経て「今あるものがある日突然失われる」かもしれない感覚は、あの日を体験したり知ったり越えてきた多くの日本人が持った感覚だろう。
そして、だからこそ永遠はないということを、「今」を大切にしようと決意を新たにしたのではないだろうか。
東京は、良くも悪くも変わり続ける都市だ。
湿地帯だった関東平野に水路を作り城を建て町を築き、大震災や空襲で焼け野原となった土地をまたイチから整備し、海を埋め立て土地を作り、ビルが建つ。
昨日見た街並みが、どんどん過去になっていく。
変化していく新宿や東京の姿。
これからも東京、そして新宿で生き続けるであろう私にとって、新海作品で描かれるその街並は観るたびにより一層懐かしさを思い起こされるものになっていくだろう。
東京を襲い続け、遂には多くの地域を沈めてしまった大雨。
その中でもたくましく通勤船を出し、”普通”に働き続ける人々はある種狂気的でもある。
でもそうやって何が起ころうとも、東京はたくましく変化し続けていくのだろう。
ただ東京の風景が現在からは大きく変わってしまったことで『言の葉の庭』『君の名は。』から続いていた、ユキちゃん先生や瀧や三葉が生きている世界の物語はここで一旦終わりなのかもしれない。
そう思うと、ちょっと寂しい。
「ドコモタワー」は、これからも形を変えずにいてくれるであろうか。
新宿駅南側にドコモタワーより高い建物が立ったその日、空を見上げた時に感じる想いもまた変わるのだろう。
長雨の続く東京で、ようやく晴れた夏の始まりの日。
映画館を出た歌舞伎町の猥雑さと空の青さが、とても眩しく美しかった。